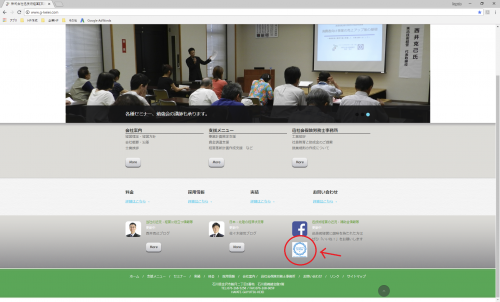こんにちは。石川県で中小企業経営のお手伝いをしている迅技術経営です。
この度、北海道で起きました地震により被災された皆様
ならびにそのご家族に心よりお見舞申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心から願っております。
また、余震のみならず、さらに大きな地震などには十分にお気をつけください。
日本は長らく様々な自然災害に見舞われてきました。
弊社のある石川県は、霊峰・白山のおかげか(皆さんそうおっしゃいます)、
幸いなことにあまり大きな災害には見舞われておりません。
しかし、ほんの10年前には能登半島地震があり、
今年の1~2月には37年ぶりの大雪が降り、福井県や石川県で多くの被害が出ました。
今後もいつ・どのような災害が自分たちの住む地域を襲うか、
どこも安全とはいえないような気がしています。
また、どこかで発生した災害等により、モノが不足するなど間接的な
影響が発生するケースも少なくありません。
会社にとっては、少しでも早く事業を再開し、供給責任を果たしていくことが重要です。
このために必要になってくるのが、東日本大震災以降注目が集まっている
事業継続計画(BCP)です。
ただ、必要とは思っていても、すぐに作らなければならないわけではない…
このような性質のものであるため、策定率は平成28年度の時点で15.5%に
とどまると言われています。
しかし、BCPと大げさに捉えるのではなく、「何かイレギュラーが発生した際の
復帰・継続方法の整理」と捉えるとどうでしょう。
メイン設備の故障、屋根の雨漏り、インフルエンザの社内パンデミック…
どうでしょう、皆様にも思い当たる節があるのではないでしょうか。
このような事態(会社にとってはとても重要な「非常事態」だと思います)に対して、
どのような流れで復帰させるのか。また、非常事態を防いだり、被害を軽減されられるのか。
これを一つ一つ考えていくことが、ひいてはその会社独自のBCPにつながっていきます。
またイレギュラーに対して策を講じることは、実は非常事態時だけに有効なのではなく、
日常的な経営改善にも有効です。
というのも、非常事態による被害を極力回避・軽減することの最大の対策は、
人間も含めて「日常的なメンテナンス」だったりするからです。
興味のある方は、中小企業庁にBCPの策定方法が結構細かく記載されていますので、
ぜひご覧ください。
示されているとおりに作っていくと、立派なBCPが出来上がるようにもなっています。
皆様も身近なところから「プチBCP」を考えてみませんか?